| | 1 | 2 | |
ウェブアクセシビリティセミナーinにいがた2004 講演録(1)
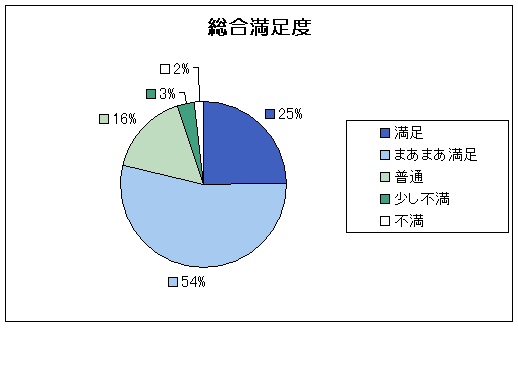
1.主催者代表あいさつ(新潟県総合政策部情報政策課長 土田茂)
最初に、本日のテーマ、ウェブアクセシビリティを取り上げた背景についてお話しさせていただく。まず第一に、近年ホームページが情報の発信や収集に大きな地位と役割を果たしていること。
二つ目に、本年6月にウェブアクセシビリティに関するJIS規格が発表されたことである。
ホームページの役割について、県の数字を紹介させていただくと、県ホームページへの外部からのアクセス数は、今年7月の1か月間で43万件、1日当たり1万4千から5千件である。これは昨年度の月平均が約20万件であり、大幅な増加である。この要因としてはブロードバンド環境の普及とホームページの内容充実によるものと思われる。こうした中、高齢者や障害者の利用も年々広がりを見せているようだが、社会との大切な接点として、重要な情報源として利用いただけるように発信者側も努力していかなければならない。
県では昨年「新潟県ホームページ作成基準」を策定し、現在ホームページのリニューアル事業に取り組んでいる。
aph 本IT&ITS推進協議会では、これまでもウェブアクセシビリティの確保の必要性について、各種セミナーや調査等を通じてその啓発に努めてきたが、この度のJIS規格化により、今後ますますその重要性について、社会の関心も高まってくるものと思われる。
本日のセミナーは、このJIS規格の内容をはじめ、アクセシビリティの確保に向けた取組姿勢や配慮すべき利用者に関する知識等々をご紹介いただくことによって、ウェブコンテンツの制作や利用にかかわる方々にとって、アクセシビリティについて理解を深める良い機会になればと考えている。
2.第一部「県内市町村ホームページの現状と課題」
講師:南雲秀雄 氏 (新潟青陵大学福祉心理学科教授)
今回は県内市町村のホームページについて調べた結果を報告したいと思う。
これまで新潟県IT&ITS推進協議会の地域におけるIT活用検討部会では、3か年度にわたってそれぞれアンケート及び点検ツールにより調査を行ってきた。特に14年度においては、実証実験として、実際にある自治体のホームページをアクセシブルなものに変えて、その効果を高齢者や障害者の方に確かめてもらうといったことも行った。
■県内市町村のウェブサイトの開設率は今年ようやく100%に達した。
■トップページの平均ファイルサイズは1年で25%ほど大きくなっている。
■昨年度のアンケート調査結果は以下のとおり。
・「ウェブサイトの作成者」は、役所内の担当部署によるところが20%、役所内のそれぞれの部署が対応しているところが7%で、何らかの形で業者が関与しているところの割合が67%であった。
・一方、「ウェブサイトの更新」については、約80%が役所内の人が行っているという結果であった。これにより、役所の人がウェブアクセシビリティの知識を持つことが非常に重要であることが分かる。
<その他、「ウェブサイトの更新頻度」、「ウェブアクセシビリティの認知度」、「配慮した具体的対策」、「ウェブアクセシビリティが反映されない理由(人手及び作業時間の不足・技術的知識の不足等)」について紹介>
■ウェブヘルパーの点検結果では、点検レベルとして「A」、「ダブルA」、「トリプルA」があるが、トップページがレベルAを満たした県内市町村の割合はわずか3%(3市町村)である。
問題点の項目としては、「画像の代わりとなるテキストが用意されていません」が最も多く、「画面の明滅する機能が使用されています」がそれに続いている。その他、「スクリプトの代わりとなるテキストが用意されていません」、「各フレームにタイトルが用意されていません」があげられる。
「画像の代わりとなる代替テキスト」については、数が多く、持続的に対処が必要であるが、デザイン・レイアウトに影響を及ぼさず、対応は難しくない。
この写真に対してどういう文字をいれたらいいかは、35文字の文学作品ととらえてALTの設定を行っていただきたい。ALTのコンテストなどもあってもいいのではないか。
「画面の明滅する機能」については、数はそれほど多くなく、一回の変更で済むものである。
「スクリプトの代わりのテキスト」についても、数は多くなく、一回の変更で済む。
「フレームのタイトル」については、市町村ホームページの30%くらいがフレームを使用しているが、フレームのタイトルを付けているところは一つしかない。目の見えない方にとっては、フレームのタイトルが分岐点の道案内をしているため、これは非常に重要である。対応は簡単であるので、是非、対応いただきたい。
■まとめ
①レベルA確保は難しくない。
②JIS規格に是非とも挑戦していただきたい。
③指針の表明とフィードバック体制を是非とも作っていただきたい。
以上を申し上げて、私の話を終えたいと思う。
ご静聴ありがとうございました。
| 新潟県IT&ITS推進協議会へもどる | | 1 | 2 | | このページのトップへもどる |