| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
5-5. 市町村のウェブサイトの活用
5-5-1. 今後のウェブサイトの活用方法
ウェブアクセシビリティとは直接関係しないが、市町村が今後どのようにウェブサイトを活用していくのか、市町村が回答した活用方法を次に示す。なお、回答した市町村名が特定されるような記述部分には○○と記した。(1) 情報発信(48件)
(a) 市内外に向けた情報発信ツールの1つとして活用するとともに、地域情報化の中心となりえるようなサイト作りを目指す。
(b) 主に観光PR。
(c) 市民が知りたいことが何でもわかるような内容を目指して、市民生活に密着した情報の送受信、観光情報の発信、情報の更新頻度を上げていくことや申請書等をダウンロードできるようにしてゆきたい。
(d) 全国版広報としての位置付けを考えていきたい。
(e) 広報誌程度の情報発信の場。
(f) 合併した後も、支所コーナーとして地域の特色を発信できれば良いと思う。
(g) 住民へのタイムリーな情報提供。
(h) 地域の情報発信の主としたい→現「有線放送」の代わり。
(i) 情報を増やしつつ、また、見やすく整理して市民の方に必要な情報を提供する。行政情報以外に、○○市関係のリンク(天気、交通機関時刻情報等)を設置する。ウェブアクセシビリティ導入の初期段階として、アクセシビリティ指針を策定する。
その他同意見 39件
(2) 交流・窓口(26件)
(a) 広報機能だけでなく、公聴機能を持ったコミニケーションツールとして活用したい。
(b) 現在のHPは観光情報中心ではあるが、今後各種申請手続きなどがわざわざ役場に足を運ばなくても行えるようにコンテンツを整備していきたいと考えている。また、HP上での住民との情報交換も積極的に行っていく。
(c) 住民参加を促すツールにしたい。電子会議室の利用、パブリックコメントなど。
(d) ○○市ホームページは、これまでの「行政主体のまちづくり」から「市民主体のまちづくり」へ転換するための橋渡し役となるために、情報公開のツールとして活用し、利用される市民にとって使い勝手の良いホームページを目指しています。
(e) 市内用や市外用、子供用など対象者ごとのウェブサイト作り、市民参加型の会議室(会員制)の設置、動画配信サービス、電子申請。
(f) 現在は、村内のインターネット接続世帯も少なく、ウェブサイトも観光情報など村外向けのページが多いが、住民向けページの充実を図り、インターネット接続世帯の増加にもつながるようにしていきたい。
その他同意見 21件
(3) その他(22件)
(a) ウェブアクセシビリティの向上を目指したい。掲載情報の内容の充実を図りたい。(同意見 他2件)
(b) 本村住民のインターネット利用は、低い状況にある。また、高速通信情報基盤の整備が遅れている地域となっている。このため、ウェブサイトの活用は、広報紙等の補完程度の位置付けで活用していく予定である。
(c) 合併後の新市で検討。(同意見 他10件)
(d) 市町村合併により、旧市町村サイトは廃止の予定。(同意見 他1件)
(e) 特に今後の発展は考えていません。(同意見 他4件)
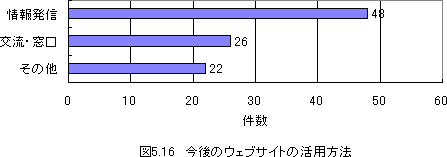
「 この回答から、ウェブサイトへの期待や位置付けが市町村により大きく異なり、かなり温度差があることがわかった。回答内容は観光PRから電子申請・電子会議など幅広い。 やはり情報発信という回答が最も多かったが、観光PRなどに代表される市町村外への発信と、住民向けの情報発信という2つの志向がみられた。さらに後者の発展形として、住民との交流やサービス窓口に活用するという意見も多い。具体的にはウェブサイト上での住民との情報交換や住民参加型の電子会議、各種手続きの電子申請などである。これらのコンテンツにおいては情報発信以上に充分なウェブアクセシビリティが確保されなければならない。障害者や高齢者を含めた全ての住民にとってディジタルデバイド(情報通信の利用面での格差)の無いウェブサイト構築を期待する。
| 新潟県IT&ITS推進協議会へもどる | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | このページのトップへもどる |