| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
5-4. ウェブアクセシビリティの認知とその実践
5-4-1. ウェブアクセシビリティの認知度
担当者のウェブアクセシビリティの認知について図5.13に示す。内容を理解し、ウェブアクセシビリティ対策も実践している市町村は12%である。一方、ウェブアクセシビリティを全く知らない市町村はわずか9%でウェブアクセシビリティという言葉は比較的浸透していることがわかる。一方で、おおよその意味は知っているが詳しい内容を知らないと回答した市町村は42%で、公的機関におけるウェブアクセシビリティやデジタルディバイド(情報通信の利用面での格差)による問題が十分理解されていないことが窺える。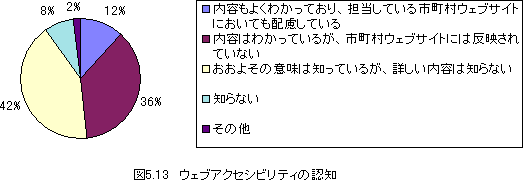
5-4-2. ウェブアクセシビリティに配慮した具体的対策
市町村が回答したウェブアクセシビリティに配慮した具体的対策を次に示す。(1) 指針作成(11件)
(a) 「代替テキスト」「画面や文字を点滅させない」など、指針を作成して対応。
(b) 新市におけるホームページでは、文字を大きく表示する機能や色盲の方でも区別しやすい色でのページ作成を現在進めています。
(c) alt属性使用、ページタイトルをつける、横スクロールさせない、サイトマップ、位置情報を載せる、機種依存文字の不使用、フレーム使用を控える、新しいウインドウを開かない。 その他同意見 他8件
(2) ツールの利用(2件)
(a) 読み上げソフトや総務省のウェブヘルパーに対応。
(b) ウェブヘルパーを使い最低限の配慮はした。
(3) その他(1件)
(a) 月2回更新している広報誌を視覚障害者等の方々が音声で聞けるように【テキスト】形式のものをアップロードしている。まだまだ、十分ではないが今後ともより充実を図っていきたい。
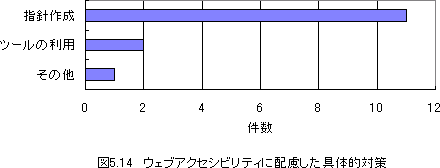
ウェブアクセシビリティを確保するために適切な指針を作成し、実行している市町村が見られる。このうち数市町村は、昨年度、本部会が実施した「ウェブアクセシビリティセミナー」及び「ウェブアクセシビリティ改善講習」(※9)の参加市町村でもある。
※9) 新潟県IT&ITS推進協議会 地域情報化委員会 地域におけるIT活用検討部会 平成14年度活動内容
ウェブアクセシビリティセミナー結果報告
ウェブアクセシビリティ改善講習会結果報告
| 新潟県IT&ITS推進協議会へもどる | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | このページのトップへもどる |