| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|
Q16 今後注目の携帯電話の機能(複数回答) |
|
|
|
|
回答数 |
% |
|
QRコード |
23 |
29.1% |
|
GPS機能 |
54 |
68.4% |
|
カメラ機能 |
28 |
35.4% |
|
テレビ電話機能 |
22 |
27.8% |
|
テレビ放送受信機能 |
14 |
17.7% |
|
財布機能 |
13 |
16.5% |
|
無線LAN機能 |
9 |
11.4% |
|
その他 |
4 |
5.1% |
|
無回答 |
9 |
11.4% |
|
計 |
79 |
100.0% |
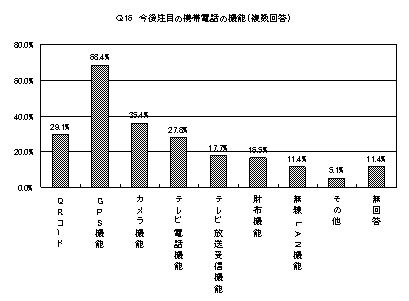
Q17.今後の携帯電話への期待は、「電子申請のツール」と「カメラ機能、GPS機能を使った高度情報処理ツール」がそれぞれ50.6%で上位にあげられている。
|
Q17 今後の携帯電話への期待(複数回答) |
|
|
|
|
回答数 |
% |
|
電子申請のツール |
40 |
50.6% |
|
PCのHPに代わる行政情報発信ツール |
36 |
45.6% |
|
メール機能、カメラ機能による住民とのコミュニケーションツール |
27 |
34.2% |
|
カメラ機能、GPS機能を使った高度情報処理ツール |
40 |
50.6% |
|
テレビ放送受信機能を活用した情報配信ツール |
15 |
19.0% |
|
財布機能等を活用した決済ツール |
11 |
13.9% |
|
その他 |
3 |
3.8% |
|
無回答 |
3 |
3.8% |
|
計 |
79 |
100.0% |
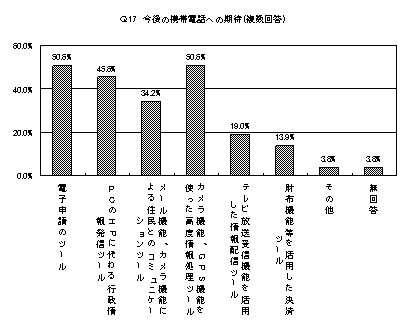
Q18.電子自治体、携帯電話の利活用に関わる問題点(自由意見)
・町村部からは携帯電話の不感地域解消を望む声が多く寄せられている。
・電子自治体によるサービス向上を目指す市部と、基盤整備を急ぐ町村部の温度差が大きい。
|
Q18 自由回答 |
|
|
|
|
回答数 |
% |
|
記入有り |
32 |
40.5% |
|
計 |
79 |
100.0% |
(3)調査全体のまとめ
庁内のIT化、情報化の概況については、平成14年度調査と比較すると急速な進展が見られ、各自治体における庁内パソコン(ITインフラ)の整備はほぼ一人一台体制となっている。一方で、ホームページを利用した住民に対する情報発信の状況は自治体によって取組に差異が見られ、更新頻度、更新方法ともに回答が分かれた。これについては、運営体制とあわせて、詳細な分析が必要である。
今回、初めて携帯電話の利活用について調査を行ったが、現状では通話機能の利用がほとんどで、通話以外の利用(画像機能、メール機能、GPS機能等)はごく少数であることがわかった。携帯電話のサイトによる情報発信は、3分の1に当たる29団体で実施されているが、これについても更新頻度が不定期の自治体が多く、アクセス数の把握も半数以上が行っていないことが明らかになった。今後の携帯電話の利用については、GPS機能に強い関心が寄せられている。自由回答においては携帯電話の不感地域解消を希望する意見が多く、携帯電話の利用環境の急速な整備が望まれている。
電子自治体の推進と、携帯電話の利活用は、今後密接な関係となることが予想され、取組状況も相関を持つことが予想される。先進的な利用状況についてもヒアリング調査などを行い、電子自治体に関する携帯電話の有効活用の方策について、実験的な取組も含めて今後の継続的な研究が必要と考えられる。
| 新潟県IT&ITS推進協議会へもどる | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | このページのトップへもどる |